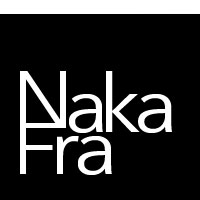■モーツァルトとベートーヴェンの段差から(そしてワーグナー)
中野:『ハムレット』はどうですか、最近何かやりました?
長島:たまたまですけど、今年、大学の前期授業で取り上げてました。それは少し伏線があって、芸術とは何かみたいなところをきちんと言語化できるように、いろいろ勉強し直そうというソロプロジェクトが自分の中でこの数年走っていまして。
中野:それは個人的な勉強?
長島:そうです。演劇史と音楽史をチャンポンで勉強し直しています。そうすると、すごくよく分かることがいろいろあって。今の芸術家像みたいなものがどこからスタートしているか、芸術とはこういうものだというイメージやコンセンサスがどのあたりから出てきて、そのあとどう変わっているかとか。もう少し言うと、文学と音楽と演劇を行き来しながら考えると結構考えられそうな。あと、哲学ですね。美術は、そこまで追いつかなくて、単に手が回っていないだけなのですが。
中野:音楽史だと、いわゆるクラッシック?
長島:はい。例えば、モーツァルトとベートーヴェンの間にはものすごい段差があって、そこで何か後戻りできない出来事が起こっている気がします。
中野:段差……。ベートーヴェンが何かやってしまった?
長島:あの二人は14歳差なんだけど、そこで決定的なことがありまして。ベートーヴェンがやったというより、ベートーヴェンを取り巻くところで何か起こっています。社会の変化に伴って、芸術家の地位が変わっています。簡単に言うと、モーツァルトは天才だったけれども、雇われ職人として抱え込まれるしかなかった世代で、一方ベートーヴェンは最初のフリーランスのアーティスト。それは才能とかの問題ではなく、時代のコンセンサスとステータスの問題なのですが、モーツァルトは誰かに雇われていて、大抵は貴族や権力者、王侯貴族、または教会ですね、とにかく召し抱えられ注文を受けて何かつくる、抜群のクオリティーのものを納品し続ける職人のラスト世代。それをやめたかったんだけど、叶わなかった。一方ベートーヴェンも、貴族がスポンサーについているけれども、それはパトロンないしは支援者で、ベートーヴェン自身がつくりたかったものに対して支援が行く。受注じゃない。その主従関係の逆転が、この二人の間で起こっているんです。
中野:……おかしなことを言いますけど、今の話を聞いて、自分が大学で働いている理由がわかった気がします。僕は、前からモーツァルトが好きで、なるほどモーツァルトになりたがってるんだな……と思った。さらに無理やり話をつなげると、例えば、ベートーヴェンからハラスメントが始まったとか?
長島:ある意味ではそうかもしれません。アーティストが加害者になりうる立場を手に入れた。もう少しいくとワーグナーという問題があります。
中野:あいつかぁ…。
長島:余談ですが、80年代にイギリス・オーストリア・ハンガリーの合作で、ワーグナーの伝記が、8時間近くあるTVドラマになっています。リチャード・バートンという、ハムレットも演じている高名なイギリスの名優が、ワーグナーをやっているんです。ワーグナーってひどい、悪いやつなのだけど、リチャード・バートンがほんとにいい味を出していて、なんか見てしまうんですよね。愛してしまうというか、愛嬌があって。
中野:でも、そういったところに愛すべき点とかを見つけてしまうときっとハラスメントはなくならないんでしょうね。でも、愛すべき点もあると。
長島:あれは、やばいです。
中野:愛すべきで言うと、例えば日本の「寅さん」。いずれあれもハラスメントということになって、あれだけ不謹慎な、倫理を無視したものが長年日本人の心のよりどころとされてきたなんて、だから日本は遅れているんだというようになっていくのかな?
長島:ハラスメントの問題は雑に言えないけれども、パワハラに関しては上下関係がポイントで、寅さんは上に立っていない人だから、上下関係にはなっていないですよね。ちょっと分かりませんが、権力関係がないからパワハラではないのではないのでしょうか……。
中野:ワーグナーはパワハラだった?
長島:作曲家が権力の頂点に登り詰めて王侯貴族をかしづかせる感じですから、立場的にはありえます。
中野:今、ほんとに無意識に「ワーグナーやべえ、格好いい!」と言いかけたけれども、これは控えないといけないか……。
長島:どこをどう評価するかの問題なので、それは言ってもいいと思いますが。彼はバイロイトという、それまでパッとしなかった田舎の町に自分で劇場を建てて君臨しました。自分の作品のための城を建てたのです。
中野:ある演劇人の名前が浮かんでいるけどやめましょう。
長島:きっと、そのモデルですよ。
中野:そういうことですね。
長島:ワーグナーは一つのモデルです。