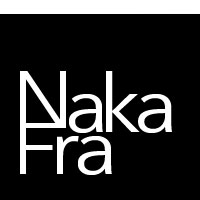小野小町という名前を聞いたことがありますか?
あまりにも美しい、絶世の美女として語り継がれている女性で、今でもその名前は美しい女性の代名詞となっています。彼女は平安時代の歌人(和歌を詠む人のこと)で、詠んだ歌は百人一首にも選ばれています。
花の色は うつりにけりな いたづらに
わが身世にふる ながめせしまに(百人一首第9番)
この歌を詠んだのは小野小町です。小町の歌だと知らずとも、聞いたことのある人は多いかもしれませんね。
そのあまりの美しさに、こんな伝説が創られています。
小野小町に恋した一人の男。彼のことを真に受けなかった小町は彼に、「百夜通えばあなたのものになる」と言いました。彼は約束通り毎夜小町のもとへ通いました(百夜通いと呼ばれています)。しかし最後の夜、ついに恋を果たせず息絶えてしまうのです。
そしてその伝説から創られた能(能面と呼ばれる仮面を使い、舞踊や音楽を中心に進行される演劇のこと)の作品が「×××××」です。×××とは、仏や死者を供養するための塔、もしくはお寺へ向かう参道の道しるべのことを言います。
あらすじはこうです。
===
年老いた女が×××に腰掛けているところへ僧(お坊さんのこと)が通りかかり、仏を粗末にしているとして×××から立ち上がるよう言い聞かせます。しかし女は逆に僧を言い負かしてしまいます。女はかつて美しかった小町だったのです。小町はやがて、かつて自分に恋をし、最後の夜に息絶えた男の怨念によって狂乱してしまいます…
===
さらに、この作品は作家の×××××によって近代の劇に翻案(原作を生かして作り直すこと)されました。作品名は変わらず「×××××」。1956年に××社から出版された『×××××』という本の中の一作です。
舞台は公園となり、原作にあった×××はベンチとして、僧は詩人として登場します。そして老婆は近代の「小町」として登場し、また詩人はあの百夜通いの男と重ねられ、まるであの伝説が繰り返されているかのように描かれているのです。
千年以上前の歌人、小野小町。彼女の伝説は時を超え空間を超え語り継がれてきました。××の×××××で、詩人は最後に「僕は又きっと君に会うだろう、百年もすれば、おんなじところで……」と言います。
もしかすると、今もどこかで小町伝説は繰り返されているのかもしれません。
小学生にもわかる作品解説『×××××』
★★☆2.5 (予習復習に是非ご活用ください) byスタッフ 久木野実玖
*Bプロの演目は公演当日のお楽しみ