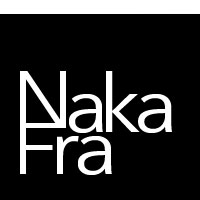日本の柴幸男さんが書いたお話です。
書かれたのは2009年ころ。今から7年くらい前です。
これは、ひとつの星が生まれてから死ぬまでと、ひとりの女の子が生まれてから死ぬまでのお話です。
女の子は団地で家族と暮らしています。そして女の子は宇宙にうかぶ地球でもあります。
いろんなものが生まれて、出会って、別れて、いなくなって、めぐりめぐる。
時報(時間を知らせる音のことです)とラップ(リズムに乗ってしゃべるようにうたいます)とともに進みます。
人間と星の一生を重ねあわせて、そこにおこる小さな、でも誰かにとってはとても大きな出来事を描いたお話です。
2010年、岸田國士戯曲賞という演劇の大きな賞をとりました。本にもなりました。
本にはことばが楽譜のように書かれています。簡単なように見えますが、実際にやろうとするととても難しいです。
たとえば、組み体操や吹奏楽の合奏のように、ひとりが失敗するとくずれてしまいます。音楽と一緒に進みますから、リズムやテンポも大切です。
何度も練習をかさねる地道さが必要ですが、ただ正確にできればいいというわけでもありません。
その難しさは宇宙の果てしなさを想像させます。
また、アメリカのソーントン・ワイルダーさんが書いた『わが町』というお話があります。
ある町の、ありふれた日常。町に住む女の人は恋をして結婚します。そして死んでしまいます。
彼女は生きているころに一日、戻ってみます。
そこで見たのは、ほんのささいな「ふつうの日」でした。
そしてその「ふつうの日」に気づかず毎日を過ごす、生きている人たちでした。
死んだ人たちはこの世を想って言います。
「ああ、人生ってまったくひどいものね……そのくせ、すばらしかったわ」
『わが星』はこの『わが町』のアイディアがもとになっています。
女の子は死んでいきます。星も死んでいきます。
人にとっても星にとっても、生まれてから死ぬまではあっという間かもしれません。
そんななかで、わたしたちの生活や、世界は、どんなふうに過ぎ去っていくでしょう。
『わが町』が書かれたのは1938年。それから70年ほど経って『わが星』が書かれます。
演劇も、星と同じようにめぐりめぐるようです。
小学生にもわかる作品解説『わが星』
★★☆2.5 (予習復習に是非ご活用ください) by スタッフ東彩織