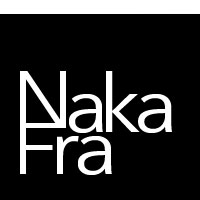はじめて岡本綺堂を読んだのは、大学の授業でだったかと思う。
近代劇についての講義でだったと記憶しているが、
話の流れでなぜか新歌舞伎の話となり、皆で『修善寺物語』を読み合わせた
(しかし、どうして「修善寺」だったのだろう…?)。
二十歳そこそこの僕にとっては、おもしろくもつまらなくもないものだった。
25年ほど前の話だ。
『半七捕物帳』も含め、綺堂を好んでパラパラ読むようになったのは、
今から10年ほど前で、長島確のすすめがきっかけだった。
当時、着任した新設の短大の図書館に、なぜか岡本綺堂の全集が置いてあり、
それを見つけた長島が、「うわー…奇妙なものがあるなあ…」と目を輝かせた。
たしかに、まだ蔵書がほぼない図書館の中で、岡本綺堂全集は異様な存在感があった。
久々に読む綺堂は、もちろんかつてと何も変わっていなかったが、
今度は身体にスルスルと入ってきた。
こちらのどこかが変わったのだろう。
きれいな文章だなあ。
それ以来、岡本綺堂に感じるのはいつもそれで、読むたびに少しだけ背筋がのびる。
同じく、探偵物や怪談を得意とする江戸川乱歩の文体も大好きなのだが、
あちらは、読み進めるうちにちょっとだけ猫背になる。
今回の公演もいつものごとく、
原案を記載してはいるものの、
やはり「えらく独自な」ものに成り果てるかと思う。
それでも、私が感じた背筋の伸びだけは死守しようとつとめた。
これが私なりの、精一杯の岡本綺堂の上演です、と。
それはそれとして、
短い回数になるが、
長島、東らと、いくつか綺堂の文章を紹介したい。
身体に入るか、入らぬか。
背筋が伸びるか、縮まるか。
お付き合いいただきたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「はじめに」中野成樹 2017.9.22